- 犯罪に巻き込まれる危険性を知る
- 自宅でも事故は起こる?安全を確保する
- 新しい制度で安全は確保されるのか
□犯罪に巻き込まれる危険性を知る
子どもたちは、身体的・精神的に未熟であり、自分自身の安全を守る能力が発達していないため、大人に比べて危険にさらされやすい存在です。
そのため、子どもの安全を確保することは、社会全体の責任であることは言うまでもありません。
しかし、近年の子どもが巻き込まれる事件の推移を考えると、子どもたちが被害者となる犯罪や事故が減少傾向にある一方で、
一部の種類では増加傾向や横ばい傾向にあることが分かります。このような状況下で、我々は子どもたちの安全に関する課題に対して、真剣に向き合い、解決策を模索する必要があります。
平成20年から令和2年までの10年間で、
13歳未満の子どもたちが被害者となった刑法犯の認知件数は、約3万件から約2万件に減少しました。
しかし、全被害件数に占める子どもたちの被害件数の割合は、
約6%から約8%に上昇しました。
これは、犯罪が減少する中で、子どもたちが被害者となる確率が高くなっていることを示しています。
一方で、子どもたちが被害者となる性犯罪に関するデータを見ると、平成20年から令和2年までの10年間で、
子どもたちが被害者となる強姦、強制わいせつ、強盗強姦及びわいせつ目的略取・誘拐に関する犯罪の認知件数は、
約1,500件から約1,000件に減少しました。ただし、前年比では増減が交互に起こっており、安定的な減少傾向ではありません。また、全被害件数に占める割合は約1%程度で変わりませんでした。
さらに、児童虐待に関するデータを見ると、
平成20年から令和2年までの10年間で、児童虐待事件の検挙件数は約200件から約400件に増加しました。
また、検挙事件に係る被害児童数も約200人から約400人に増加しました。これらの数字は、平成11年以降で最多を記録しており、児童虐待の現状は極めて深刻です。
以上のように、子どもたちが巻き込まれる事件の推移は、全体的には減少傾向にあるものの、一部の種類では増加傾向や横ばい傾向にあることが分かります。このような状況下で、我々は子どもたちが安心して成長できる環境づくりに取り組む必要があります。たとえば、家庭や地域社会での啓発活動や、学校での教育プログラムの充実、警察との連携強化などが考えられます。
子どもたちが安心して成長できる環境を作るために、私たちも積極的に行動しましょう。地域社会や家庭、学校など、さまざまな関係者が協力して、子どもたちの安全を守るための環境づくりを進めることが必要です。そのために、私たちは、子どもたちが抱える問題に真摯に向き合い、解決策を模索することが重要です。子どもたちが安心して成長できる社会を作るため、今一度、私たちができることを考えてみましょう。
□自宅でも事故は起こる?安全を確保する

幼児は、好奇心旺盛で活発に動く一方、危険を回避する能力が未発達なため、事故に遭いやすい年齢です。
特に自宅では、保護者が目を離した隙に、家具や家電、調理器具などによってケガをしたり、ボタン電池や洗剤などを誤って飲み込んだりする恐れがあります。そこで、どのような事故が多く発生しているのか、そしてどのように予防することができるのかを見ていきましょう。
さらに、警察庁が令和2年に発表した交通事故発生状況によると、幼児(未就学児・就学児)の死者・重傷者数は238人でした。この数字は、幼児の交通事故が深刻な問題であることを示しています。幼児が交通事故に巻き込まれることは、多くの家庭にとって大きな心配事であり、その事故の原因を正確に把握することが重要です。
幼児の交通事故は、歩行中、自動車乗車中、自転車乗用中など、様々な状況で発生しています。
特に、歩行中の死亡事故では、道路横断中以外が63.1%を占めており、法令違反や幼児の判断ミスなど様々な原因が考えられます。幼児のひとり歩きと飛出しによる死亡事故が55.2%を占めていたことから、幼児が歩行中に交通事故に遭遇する可能性が高いことが分かります。事故を防ぐためには、幼児に対する適切な指導や監視が必要です。
また、自動車乗車中の死亡事故でも、チャイルドシートの不適正使用及び不使用が81.5%を占めています。チャイルドシートを適切に使用しないことで、幼児が事故に巻き込まれるリスクが高まります。チャイルドシートを正しく取り付け、使用することは、幼児を守るためにも重要なことです。
自分でできる安全対策
- 家の中には、階段や窓に手すりや柵を設置して、家具や家電を安定させることが必要です。これにより、子供たちが転倒したり、窓から転落するなどの事故を未然に防ぐことができます。また、調理器具や刃物などは子どもの手の届かない場所に保管し、使用後はすぐに片付けるようにしましょう。これにより、子供たちが誤ってこれらの危険なものを取ったり、怪我をしたりする可能性を低くすることができます。
- ボタン電池や洗剤などは密閉容器に入れて、子どもの目につかない場所に保管し、使用後はすぐに捨てるようにしましょう。これにより、子供たちがこれらの物質を誤って飲み込んだり、手に触れたりすることによって、健康に悪影響を及ぼす可能性を低くすることができます。
- 子どもが一人で遊んでいるときには、常に目を離さず、危険な場所や物を教えて注意するようにしましょう。これにより、子供たちは安全に遊ぶことができ、事故を防ぐことができます。
- 外出時には、子どもと手をつないで歩くか、ベビーカーやチャイルドシートを適正に使用するようにしましょう。これにより、子供たちが車や自転車にひかれたり、転倒したりすることを防ぐことができます。
- 道路横断時には、信号や横断歩道を守り、左右を確認してから渡るようにしましょう。子どもに交通ルールやマナーを教えて身に付けさせることも重要です。これにより、子供たちが交通事故に巻き込まれる可能性を低くすることができます。
保護者対象者は、子どもの安全と健康を守る責任を持つため、幼児の事故や交通事故を予防するために様々な対策を徹底する必要があります。まず、保護者は、子どもの視点に立って、危険を見つけて排除することが重要です。家庭内での事故を防ぐためには、家庭環境の安全対策が欠かせません。家庭では、ほんの少しですが、飲み込み事故などが多く発生しています。階段の安全対策など、家庭内の危険箇所に対して注意を払い、正しくな対策今日しましょう。
また、万が一事故が発生した場合は、迅速に救急車や警察に連絡し、適切な処置を行うことも重要です。 、子どもの安全と健康を守ることができます。
幼児の交通事故についても、適切な対策をとることが必要です。 幼児は歩行中や自動車乗車中などで交通事故に巻き込まれることがあります。 このような事故を防ぐためには、チャイルドシートの適切な使用保護者の方々は、子どもの安全を常に意識し、事故を防ぐために心からの努力をしましょう。
このような徹底することで、幼児の事故や交通事故を予防することができます。保護者の皆様にとって、子どもの安全と健康は非常に重要なテーマです。私たちが示した内容が皆様のご参考になれば幸いです。
参照: 消費者庁「家の中の事故に気を付けましょう!」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_035/
参照: 警察庁「幼児・児童の交通事故発生状況」 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bunseki/kodomo/020324youjijidou.pdf
□新しい制度で安全は確保されるのか
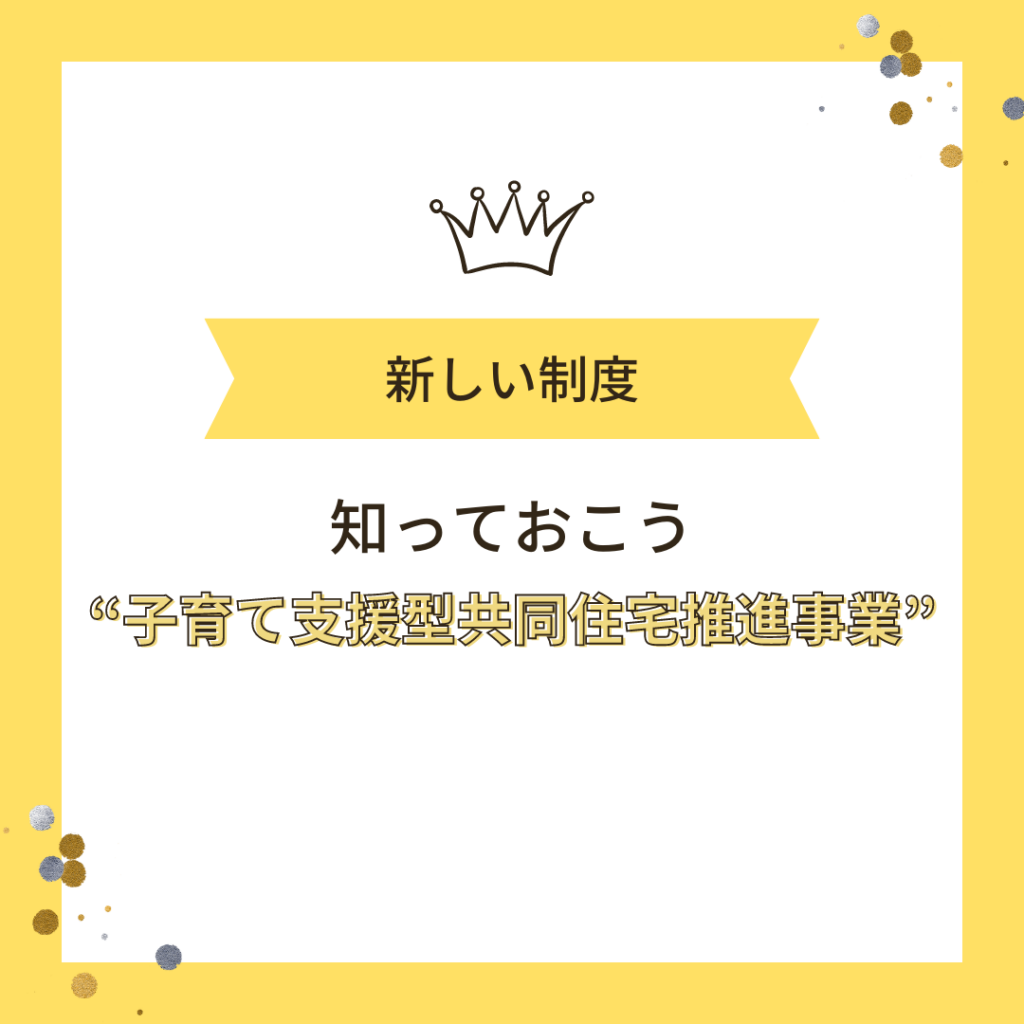
子育て支援型共同住宅推進事業
子育て世代の住宅ニーズに対応するために、国や自治体が支援する事業です。
この事業は、子育て中の家庭が安心して暮らせる住環境を整備することで、出生率の向上や少子化の進行を防ぐことを目的としています。しかし、この事業は単に子育て家庭のための住宅を提供するだけでなく、その他のメリットもあるのです。
例えば、子育て支援型共同住宅の建設や改修を行う場合、国や自治体から補助金や融資を受けることができます。
これにより、アパートのオーナーは建設費や家賃を抑えることができ、結果的に借りる人たちも家計の負担を軽減することができます。また、子育て支援型共同住宅では、共用スペースや託児施設などの子育て支援施設を備えています。
また、子供の安全確保に関する改修工事に関しても補助金が設定されており、転落防止の手すり等の設置や防犯性の高い玄関ドア等の設置など即効性の高いものにも利用できる制度なので、子供の安全のためにもチェックしておくことをおススメします。
子育て支援型共同住宅推進事業は、子育て世代に直接的な改善をされる制度ではないですが、この機会に子供が危険と隣り合わせであることをもう一度知って頂いて、個人が取れる対策と日々の積み重ねを大切にしていただければと思います。
~他の記事~
- 子供が産まれたけど。やっぱりワンオペ育児

- 産後のダイエットは必要?産後多くの人が痩せるワケ

- アルファベットを覚える為の学習方法10選。幼児教育の基本

- 補助金で解決?オーストラリアと家庭内暴力の実情

- アメリカと中国の子供どっちがお小遣い多いか知ってますか?日本はお金持ち説
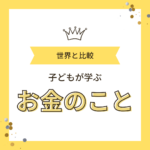
- 子供に使わせてますか?電子マネートラブルはこれからの親の悩み

- TikTokトレンドのベッド・ロッティングでストレス発散するZ世代
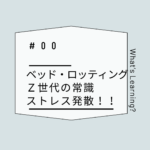
- 夫に失望する。子育ては夫婦の問題と分かっていない

- 実家で子育ては失敗する。育児が楽になるという迷信を信じた結果
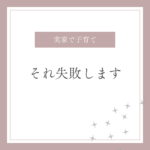
- すぐに怒っちゃう。子どもの精神力が根付く方法

- 勉強とスポーツの子育て二刀流。失敗しやすい理由はこれ

- ほらね、起業家になるなら大学に行くな?子供の進路を考える
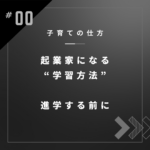
- 子どもにも妊婦にも悪影響?シーシャとスヌース知ってますか

- この夏危険な感染症は、ヘルパンギーナだけじゃない?夏休みに気を付ける
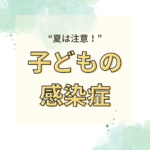
- 親注意?AIやアバターが子供に与える影響は深刻

- 子育てに影響?資本主義と子供の教育は密接にかかわる「ショック・ドクトリン」
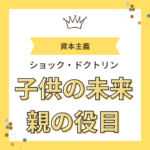
- 将来の夢は社長?MBTI式教育で起業家を育てる

- これほど便利?5Gは子育てアップデート世界が変わる

- イジメ問題とその余波を見る:危機に瀕したノースウェスタンフットボール

- 脳老化予防はKlotho(クロトー)を増やすこと。子どものころから気を付ける



