- ひとり親は主流?日本の離婚率を調査
- 国の手当や“助成金”など有効活用
- “親権”は“養育費”は?離婚する前にチェック
□ひとり親は主流?日本の離婚率を調査
ほとんどが母子家庭、父子家庭はわずか0.8%??
日本の片親の人数と割合
厚生労働省が令和3年度
実施した全国ひとり親世帯等調査によると
- ひとり親世帯(母子世帯・父子世帯)の数
約1,240万世帯で、全世帯の約10.4% - 母子世帯は
約1,230万世帯で、全世帯の約10.3%、
ひとり親世帯の約99.2% - 父子世帯は約10万世帯で、
全世帯の約0.1%、ひとり親世帯の約0.8%
年間の推移を見ます。
離婚率は年々増加し、片親の世帯は平成23年度から令和3年度までの10年間で約20万世帯増加。
母子家庭に関しては平成23年度から令和3年度まで毎年増加傾向にあります。
父子世帯は平成23年度から平成28年度までは減少傾向にありましたが、平成29年度から令和3年度までは横ばい。
□国の手当や“助成金”など有効活用

ひとり親は金銭的な面でも非常に苦労をしています。
育児と仕事を両立するわけで、もちろん仕事もがっつりと働けない方が多いです。その為、国や地方の手当が非常に重要になります。
~全国~
- 児童扶養手当:
ひとり親の子供養育の費用について国から支給する制度。子どもが18歳(高校生は20歳)まで受給できます。支給額は子どもの人数や所得によって異なりますが、最高で月額43,160円(第1子)です。詳細はこちら - 母子家庭自立支援給付金・父子家庭自立支援給付金:
ひとり親が看護師や保育士などの資格取得や高等学校卒業程度認定試験合格などを目指すために利用する給付金。
支給額は受講する講座や試験によって異なります。
最高で月額50,000円です。詳細はこちら - 高等職業訓練促進給付金:
ひとり親が高等職業訓練(専門学校や大学など)を受けるたに一時的な生活費を支給。
支給額は受講する訓練や所得によって異なりますが、最高で月額100,000円。詳細はこちら - ひとり親家庭等日常生活支援事業:
ひとり親が就労や病気などの理由で子どもの保育や家事を行えない際の、家庭生活支援員が生活援助や保育サービスを提供する制度。
利用料は所得によって異なりますが、
最高で月額10,000円です。詳細はこちら - ひとり親家庭等生活向上事業:
ひとり親が子どもの学習支援や情報交換などを行うために、地域の団体やボランティアが支援する制度。費用は無料です。詳細はこちら
□“親権”は“養育費”は?離婚する前にチェック

夫婦の離婚は一大事で、非常に体力の使う手続きです。
主に“親権問題”と“養育費問題”です。
親の親権とは、子どもの監護や教育に関する権利や義務を持つことを意味します。つまり一緒に住める権利です。
離婚や別居などで夫婦が別れる場合、子どもの親権者を決める必要があります。親権者は、子どもの住所や学校、医療などについて決定します。また、親権者は、子どもの財産を管理したり、子どもに代わって契約を管理できます。
ほとんどの場合が女性が親権を持っていますが、
親権を持つ基準としては
- 子どもの意思:
原則は子供の意見第一です。こどもが意思表示できない年齢だったりする場合や意思が不明慮、またあからさまに子供によくない親でなければこどもの意見が最重要です。 - 子どもの養育環境:
もちろん住み心地の良い方がいいです。ただ日本のひとり親の支援制度を使えば家が無くなるまでのことはないので、そこまで気にする必要はないと思いますが、一応は子どもの健康や安全、教育や生活などに影響する環境が良好な方が親権者に適していると考えられます。
“養育費について”
一般的にあ養育費は子供が小さいほど金額が高く設定されます。
金額についてはゼロ円~最高15万円/月ぐらいが一般的です。養育費を支払う側の親の年収などに考慮して金額を相談します。
親権者や養育費を決める時は、子どもの幸せを第一に考えることが大切です。子供の将来を考え自分の感情や利益にとらわれず、冷静に判断するように頑張りましょう。
~他の記事~
- 子供が産まれたけど。やっぱりワンオペ育児

- 産後のダイエットは必要?産後多くの人が痩せるワケ

- アルファベットを覚える為の学習方法10選。幼児教育の基本

- 補助金で解決?オーストラリアと家庭内暴力の実情

- アメリカと中国の子供どっちがお小遣い多いか知ってますか?日本はお金持ち説
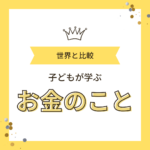
- 子供に使わせてますか?電子マネートラブルはこれからの親の悩み

- TikTokトレンドのベッド・ロッティングでストレス発散するZ世代
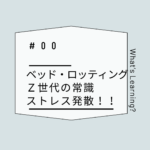
- 夫に失望する。子育ては夫婦の問題と分かっていない

- 実家で子育ては失敗する。育児が楽になるという迷信を信じた結果
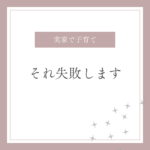
- すぐに怒っちゃう。子どもの精神力が根付く方法

- 勉強とスポーツの子育て二刀流。失敗しやすい理由はこれ

- ほらね、起業家になるなら大学に行くな?子供の進路を考える
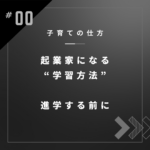
- 子どもにも妊婦にも悪影響?シーシャとスヌース知ってますか

- この夏危険な感染症は、ヘルパンギーナだけじゃない?夏休みに気を付ける
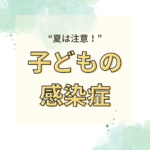
- 親注意?AIやアバターが子供に与える影響は深刻

- 子育てに影響?資本主義と子供の教育は密接にかかわる「ショック・ドクトリン」
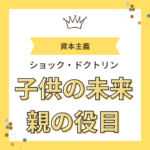
- 将来の夢は社長?MBTI式教育で起業家を育てる

- これほど便利?5Gは子育てアップデート世界が変わる

- イジメ問題とその余波を見る:危機に瀕したノースウェスタンフットボール

- 脳老化予防はKlotho(クロトー)を増やすこと。子どものころから気を付ける



