- ベビーファースト宣言とは?子供の政策
- 日本の海外の教育格差について
- 教育政策3選をまとめる
□ベビーファースト宣言とは?子供の政策
ベビーファースト宣言は、子どもの権利や福祉を優先する政策で、2019年に日本政府が発表しました。
子どもの貧困や虐待、教育格差などの問題に対処するために、様々な施策が実施されます。
- 子どもの貧困対策として、
児童手当の拡充や学校給食の無料化、学費支援.制度の拡充などを行います。これらの対策により、経済的な理由で学校や生活が成り立たない子どもたちにも支援を行うことができます。また、学校での学びや生活に必要な費用やサポートを提供することで、子どもたちが安心して学ぶことができるようになります。 - 子どもの虐待防止として、
児童相談所や保健所などの体制強化や連携を行い、虐待の早期発見や対応を行います。また、虐待を受けた子どもの保護や支援を行うことで、子どもたちが安心して暮らすことができる環境を整えます。 - 子どもの教育格差対策として、
幼児教育や学童保育などの無償化や拡充を行います。これにより、子どもたちが学びの機会を増やすことができ、教育格差の解消につながります。また、教育環境やカリキュラムなどの改善を行い、子どもたちが自分の個性や能力を伸ばすことができるようになります。 - 子どもの健康対策として、
予防接種や歯科検診などの無償化や拡充を行います。これにより、子どもたちの健康状態を改善することができます。また、食育や運動などの生活習慣の指導を行い、子どもたちが健康的な生活を送ることができるようになります。これにより、健康意識の向上にもつながります。
ベビーファースト宣言は、子どもたちの健やかな成長を目指す社会を実現するために発信されたものです。しかし、実際には、その実現にはまだまだ課題が山積しています。
たとえば、予算や人員の不足、法律や制度の整備不足などが挙げられます。これらの課題を解決するためには、政府や地方自治体、民間団体などが協力して取り組むことが必要です。
さらに、地域や家庭によっては、子どもたちが十分な支援を受けられないという問題もあります。たとえば、地方自治体での保育所の不足や、家庭内の虐待などが挙げられます。これらの問題を解決するためには、政府や地方自治体、民間団体、そして一人一人が協力して、より安心で支援のある社会を実現することが必要です。ベビーファースト宣言を実現するためには、私たち一人ひとりの意識改革が欠かせません。
□日本の海外の教育格差について

教育格差は、家庭の経済状況や地域の環境、性別や民族などの要因によって生じます。教育格差が大きい社会では、経済成長や社会的包摂が妨げられます。日本と海外の教育格差について比較してみましょう。教育の受けやすさについて見てみましょう。これは、子供たちが適切な学校やプログラムに入学できるかどうかを表す指標です。教育を受けやすい国ほど、子供たちは多様な選択肢や可能性を持つことができます。
国連開発計画(UNDP)が発表する”人間開発指数(HDI)”は、
教育へのアクセスを測る一つの指標です。
この指数は、平均寿命や所得水準などとともに、各国の人間開発水準を評価するために用いられます。
HDIは、平均就学年数と予想就学年数という二つの指標を用いて計算されます。
平均就学年数とは、15歳以上の人口が受けた平均的な教育年数であり、予想就学年数とは、現在5歳以下の人口が将来受けるであろう平均的な教育年数です。
このHDI指数により、
各国の人間開発水準が比較できます。多くの国が教育へのアクセスを向上させるために努力していますが、まだまだ改善の余地があります。
例えば、コロナ禍で学校が閉鎖された影響で、教育にアクセスしにくい状況に置かれた子供たちが多くいます。また、女性や貧困層に対する教育へのアクセスが不足している国もあります。これらの問題を解決するために、教育に対する投資が必要です。そのためには、政策立案者の協力や財政支援が必要となります。
2020年度のHDIランキングによると、
日本は189カ国中19位であり、平均就学年数は12.7年、予想就学年数は15.3年でした。この高い水準は、日本が教育への取り組みを重視してきたことの証です。
日本政府は、教育を国民の基礎的な権利の一つと位置付け、義務教育を9年間と定めています。また、高校までの教育が無料であることも、日本の教育の特徴の一つです。
一方、世界的に見ると、特に途上国では教育へのアクセスが低く、平均就学年数や予想就学年数が5年以下の国も多くあります。例えば、最下位のニジェールでは、平均就学年数は2.1年、予想就学年数は6.5年でした。このような状況を改善するために、国際機関やNGOが教育支援を行っています。また、各国政府も教育に対する投資を増やすことで、教育格差の解消を目指しています。
しかし日本では、家庭の経済状況によって、教育の受けやすさに大きな差があります。特に、高等教育において、家庭の所得水準が低いほど、進学率が低くなる傾向があります。
2019年度の日本では、
高等教育に進学する18歳の割合は全体で55%でしたが、
家庭の所得水準が最も低い25%のグループでは37%にとどまりました。OECD加盟国の中でも最も低い水準であり、家庭の所得水準が最も高い25%のグループでは75%という大きな差がありました。
日本では高等教育へのアクセスに大きな格差があるが、OECD加盟国の中では日本よりも高等教育へのアクセスが高い国がある。
例えば、韓国では全体で70%、最低所得グループでも64%の18歳が高等教育に進学しており、フィンランドでも全体で66%、最低所得グループでも58%の18歳が高等教育に進学している。これらの国では、家庭の所得水準に関係なく、子供たちが高等教育を受ける機会が平等に与えられている。
教育の質は、子供たちが学校で習得できる学力や能力を表す指標です。高い教育の質は、子供たちが将来的に社会や経済に貢献できるよう、知識やスキルを習得することを可能にします。
教育の質を測る指標として、
世界各国で注目されている国際学力調査(PISA)があります。この調査は、
OECD加盟国を中心に15歳の生徒を対象に、
読解力、数学力、科学力などの基礎的な学力
を評価するものです。PISAは3年ごとに実施され、
世界各国から参加者が集まります。
2018年度の調査には、79カ国・地域が参加しました。
PISAは、各国・地域の教育政策や教育システムの改善に役立つことが期待されています。調査結果は、教育に関する国際的な議論や比較にも利用されています。また、PISA調査においては、学力評価にとどまらず、生徒の意欲や学校生活に関するアンケート調査も行われ、より幅広い視点から教育の質を分析することができます。
しかしながら、PISA調査に対しては批判もあります。たとえば、調査対象が15歳の生徒に限られていることから、中学生までの学習成果しか評価されないなど、課題も指摘されています。それでも、PISA調査は教育に対する国際的な関心が高まる中、世界的なベンチマークとして注目を浴びています。
2018年度のPISAランキングで、
日本は読解力520点、数学力527点、科学力529点で、
世界平均よりも高く、先進国の中でも上位に位置しています。
一方、途上国では、教育の質が低く、読解力や数学力や科学力が400点以下の国も多くあります。例えば、最下位のフィリピンでは、読解力は340点、数学力は353点、科学力は357点でした。
このように見ると、日本では子供たちが高い学力を身につけているように思えますが、実際にはそうとも言えません。実は、この数値についても日本では家庭の経済状況や地域の環境によって、教育の質に大きな差があります。
□教育政策3選をまとめる
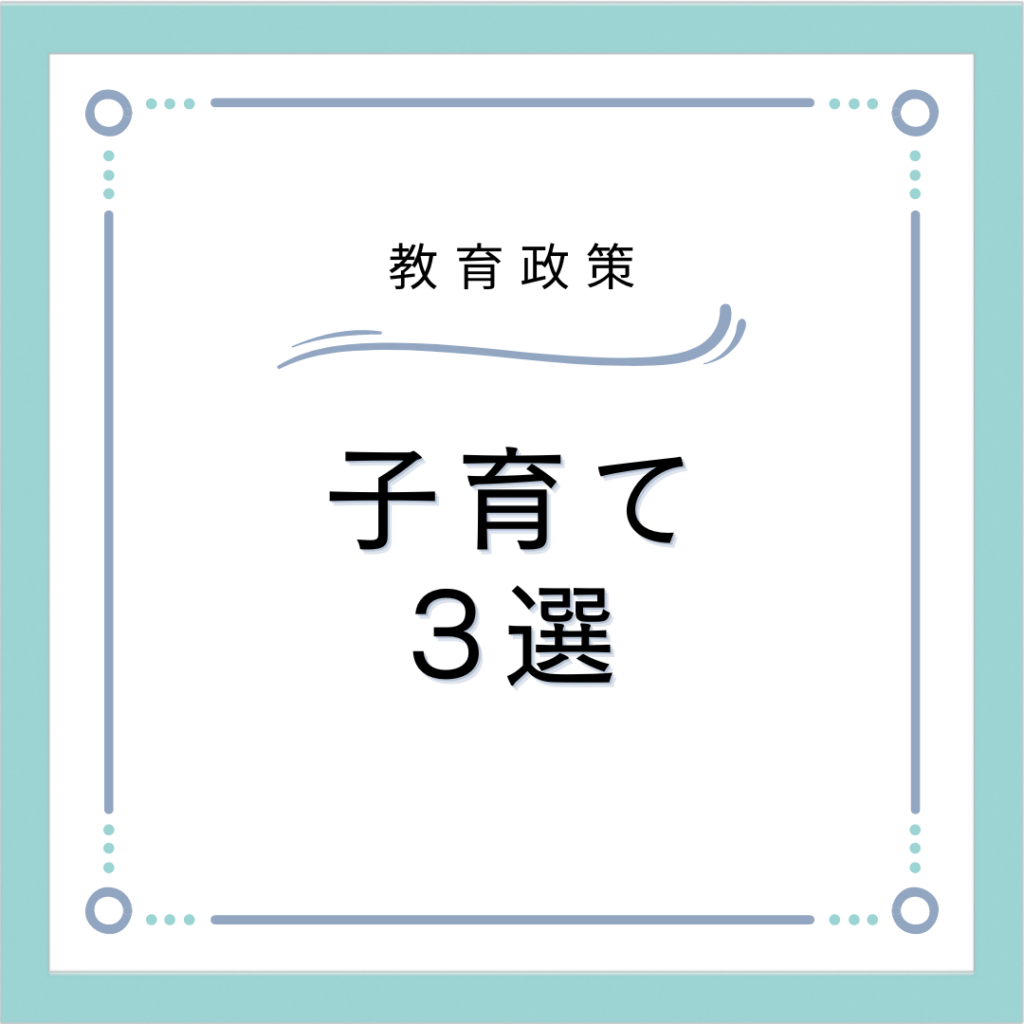
ベビーファースト宣言だけで日本が良くなるとは思えないですが、他の政策についても“3つ”ご紹介させて頂きます。
子供の権利は人権の一部であり、国際的にも保護されているものです。日本は、子供の権利を尊重し、実現するために様々な政策があります。
1. 子ども・子育て支援新制度は、
2015年4月から施行された制度で、子どもとその家族に対する総合的な支援を目的としています。
この制度による支援は、保育所や幼稚園などの教育・保育サービスの充実や無償化、子ども手当の拡充、子育て世代の住宅支援などが含まれます。
このような取り組みによって、子どもたちの健やかな成長を促し、家族の安心・安定を支援することが期待されています。
保育所や幼稚園などの教育・保育サービスの充実は、働く親の負担を減らし、子どもたちの健全な育成を支援することが目的です。また、無償化によって、経済的負担を軽減し、誰もが安心して子どもを保育所や幼稚園に預けられるようになります。
子ども手当の拡充は、子育てに必要な経済的な負担を軽減し、家計の安定を支援することが目的です。また、住宅支援によって、子育て世代が住宅を購入することが容易になり、安定した居住環境を確保することができます。
このように、子ども・子育て支援新制度は、子どもたちとその家族の幸せを目指して、様々な取り組みを行っています。
2. 子ども食堂は、
地域社会で子どもたちに無料や低価格で栄養のある食事を提供する場所で、貧困や孤立などの問題を抱える子どもたちに対して、温かい食事を提供することはもちろん、社会とのつながりや学びの機会を提供し、子どもたちが健やかに育つことを目的としています。
子ども食堂は、地域の人々が協力して運営されており、食事を提供するだけでなく、子どもたちに対して様々な支援も行われています。
例えば、
ボランティアによる学習支援やアフタースクールプログラムの提供、スポーツや音楽などのクラブ活動の開催などがあります。
政府は、子ども食堂の普及・支援に取り組んでおり、2019年度には約6,000カ所が開設されました。今後も、子どもたちが健やかに育つために、子ども食堂の拡充が求められています。
3. 子ども相談センターは、
虐待やいじめなどの危機的状況にある子どもやその家族に対して、相談や支援を行う専門機関です。
2020年度には、政府が子ども相談センターの体制強化や連携促進に努め、全国に約400カ所が設置されました。これにより、より多くの子どもたちや家族に支援を提供することができるようになりました。
子ども相談センターには、様々なサービスがあります。例えば、24時間対応の電話相談やインターネット相談があります。このサービスは、いつでもどこでも、匿名で利用することができます。また、センターでの面接相談や支援プログラムもあります。これらのサービスは、家族や地域の支援機関との連携も行われており、より総合的なサポートを提供することができます。
子ども相談センターの設置は、子どもたちが健やかに育つために必要な取り組みです。もし、虐待やいじめなどの問題が起きた場合は、子ども相談センターに相談することをお勧めします。専門のスタッフが、子どもや家族の声に耳を傾け、適切な支援を提供します。
以上が、子供の権利に対する政府の政策でベビーファースト宣言以外で具体的に3つ説明した内容です。これらの政策は、子供の権利を保障し、幸せな未来を築くために重要なものです。私たちは、これらの政策を知り、理解し、応援しましょう。
~他の記事~
- 子供が産まれたけど。やっぱりワンオペ育児

- 産後のダイエットは必要?産後多くの人が痩せるワケ

- アルファベットを覚える為の学習方法10選。幼児教育の基本

- 補助金で解決?オーストラリアと家庭内暴力の実情

- アメリカと中国の子供どっちがお小遣い多いか知ってますか?日本はお金持ち説
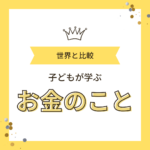
- 子供に使わせてますか?電子マネートラブルはこれからの親の悩み

- TikTokトレンドのベッド・ロッティングでストレス発散するZ世代
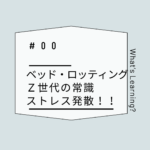
- 夫に失望する。子育ては夫婦の問題と分かっていない

- 実家で子育ては失敗する。育児が楽になるという迷信を信じた結果
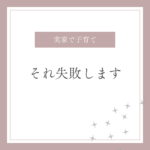
- すぐに怒っちゃう。子どもの精神力が根付く方法

- 勉強とスポーツの子育て二刀流。失敗しやすい理由はこれ

- ほらね、起業家になるなら大学に行くな?子供の進路を考える
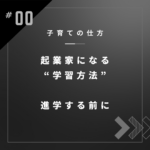
- 子どもにも妊婦にも悪影響?シーシャとスヌース知ってますか

- この夏危険な感染症は、ヘルパンギーナだけじゃない?夏休みに気を付ける
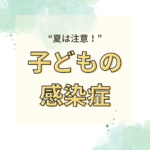
- 親注意?AIやアバターが子供に与える影響は深刻

- 子育てに影響?資本主義と子供の教育は密接にかかわる「ショック・ドクトリン」
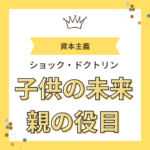
- 将来の夢は社長?MBTI式教育で起業家を育てる

- これほど便利?5Gは子育てアップデート世界が変わる

- イジメ問題とその余波を見る:危機に瀕したノースウェスタンフットボール

- 脳老化予防はKlotho(クロトー)を増やすこと。子どものころから気を付ける



