- 学校の安全計画って知ってますか?
- 小さなトラブルから大きな事故まで
- 解決方法と対策
□学校の安全計画って知ってますか?
幼稚園での集団生活には、子ども同士のけんかやいじめ、親同士のトラブル、教師とのコミュニケーション不足など、さまざまなトラブルが発生します。これらは、子どもたちの人間関係や心理的な発達に影響を及ぼすだけでなく、家庭の状況を悪化させる原因ともなるので、事前に対策をしておく必要があります。
そこで、幼稚園で報告されているトラブルの数について調べてみました。全国統計はありませんが、一部の地域や施設で行われた調査や研究から、いくつかの傾向を見ることができます。
まず、幼稚園で起きた負傷事故について
文部科学省が平成30年度まで発表していた
「学校安全調査結果」によると、平成30年度には2,015件の事故が報告されました。
そのうち、意識不明が14件、骨折が1,660件、火傷が6件、その他が330件となっています。
また、死亡事故は5件ありました。
これらの事故は、主に戸外遊びや体育活動中に発生しており、子どもたちの身体的な発達や安全意識の不足が原因と考えられます。
平成29年度と比較すると、負傷事故は約10%減少していますが、死亡事故は2件増加しています。
次に、幼稚園で起きた子ども同士や親同士のトラブルについては、文部科学省や自治体などが実施したアンケート調査から一部のデータを見ることができます。
例えば、平成28年度に文部科学省が行った
「幼児期教育・保育実態調査」では、
幼稚園で子ども同士のトラブルがあったと回答した
保護者は約4割でした。
その内容は、「けんか・暴力」(約7割)、「仲間外れ・無視」(約3割)、「悪口・嘘」(約2割)などです。
また、「親同士のトラブル」も約1割の保護者が経験しており、「悪口・陰口」(約6割)、「グループ化・仲間外れ」(約4割)、「子どもへの影響」(約3割)などが問題となっています。これらのトラブルは、子どもたちの個性や発達段階の違い、親の価値観や教育方針の相違、幼稚園の方針や対応の不十分さなどが原因と考えられます。平成27年度と比較すると、子ども同士のトラブルは約3%増加していますが、親同士のトラブルは約2%減少しています。
幼稚園で報告されているトラブルの数は、負傷事故や子ども同士・親同士のトラブルなどによって異なりますが、全体的には減少傾向にあります。しかし、それでもなお多くのトラブルが発生しており、その影響は子どもたちや保護者だけでなく、幼稚園教師や園長などにも及んでいます。幼稚園でのトラブルを防止・解決するためには、子どもたちや保護者の理解と協力が必要ですが、それだけでは不十分です。幼稚園教育要領においても、「幼稚園は,家庭や地域社会と連携し,子どもたちが安全で快適な生活を送れるようにするとともに,子どもたちが互いに仲良く遊び,友情を深め,人間関係を豊かにすることができるようにすること」と定められています。
幼稚園教師や園長は,子どもたちや保護者のニーズや悩みに寄り添い,適切な指導や対応を行うとともに,家庭や地域社会とも連携して,幼稚園でのトラブルを減らすための努力を続ける必要があります。
□小さなトラブルから大きな事故まで

実際に幼稚園に子供を通わせている4割の親がトラブルがあったと思っていると回答しているとすると、回答していない親も含めれば約半数が何かしらのトラブルに巻き込まれていると考えたほうがいいです。
また、イジメ・悪口などは被害者だけでなく“加害者”になる可能性もあるので、実際のトラブルを見て、気を付けるようにすることが大切です。
保護者として、特に子供が保育園や幼稚園にいるときには、いつも子供の健康と安全を心配するのは当然です。幼稚園は、子供たちが学び成長するための安全な場所であることが前提ですが、それでもなお問題が発生することがあります。
- いじめ
いじめはどの年齢でも起こりうるもので、保育園や幼稚園でも起こることがあります。いじめには、暴力、言葉の暴力、排除、嘘や悪口など多種多様な形態があります。いじめの原因は、子供の性格、気分、好み、嫌いなものなどによって異なりますが、支配的であることを確立したい、グループに認められたい、自信がない、などの共通の要素があります。もし、いじめが行われていると疑われる場合は、あなたの子供の担任教師や学校の管理部門と話をすることが大切です。 - 取り合いの喧嘩
幼い子供は、共有や協力する能力が形成段階にあるため、トラブルが起こることがあります。おもちゃやゲームに関する争いや友達との意見の相違から喧嘩をしてしまうことがあります。あなたの子供に、自分の気持ちや必要性を友達に伝えることを促し、妥協や協力でお互いに仲良く解決する方法を見つけるように助けてください。教師や保護者は、これらの議論を促進し、トラブル解決の指導を提供することができます。 - 病気
幼い子供は、まだ発達途上の免疫システムのために病気にかかりやすいです。保育園や幼稚園でよく見られる病気には、風邪、インフルエンザ、他の感染症、熱中症、低体温症などがあります。病気を予防するためには、あなたの子供が手洗いをする、咳やくしゃみをするときに口と鼻を覆う、病気の人と接触しないなどの良好な衛生習慣を維持するようにしてください。また、適切な服装や屋外遊び時の水分補給、日陰での遊びなどの対策も必要です。 - トイレトレーニングの課題
トイレトレーニングは、子供と親の両方にとって難しいプロセスであり、保育園や幼稚園に通う子供でも、トイレの使用に失敗することがあります。あなたの子供がトイレトレーニングで苦労している場合は、担任教師と協力して、成功するための計画を立てることが重要です。 - おむつの交換
子供がまだおむつを使っている場合、保育園や幼稚園でのおむつ交換に関して心配するかもしれません。先生たちとおむつの交換手順について話し合い、その方法について十分に納得してください。また、あなたの子供に十分なおむつとおしりふきを用意し、特別なニーズがある場合は教師とコミュニケーションを取ってください。 - ネガティブな行動
幼い子供はまだ自分自身を表現する方法を学んでいるため、殴ったり、かんだり、かんしゃくを起こすなどのネガティブな行動を示すことがあります。あなたの子供がネガティブな行動を示している場合は、担任教師と協力して、これらの行動に対処し、解決していく方法を話し合うことが大切です。 - 事故とけが
遊びの時間中、事故やけがが発生することがあります。適切な安全対策が必要です。遊び場には、柔らかい表面、子供に合わせた安全対策、大人の監視などが必要です。あなたの子供がけがをした場合は、早急に担任教師や学校の管理部門に連絡してください。 - 食事のトラブル
幼稚園では食事中にトラブルが起こることがあります。食事のトラブルの原因は、食べ物の好みによるものや、子供たちの食べるスピードの違いによることがあります。教師や保護者は、子供たちに食べることの大切さを教え、楽しく食事をする環境を作ることが重要です。
□解決方法と対策
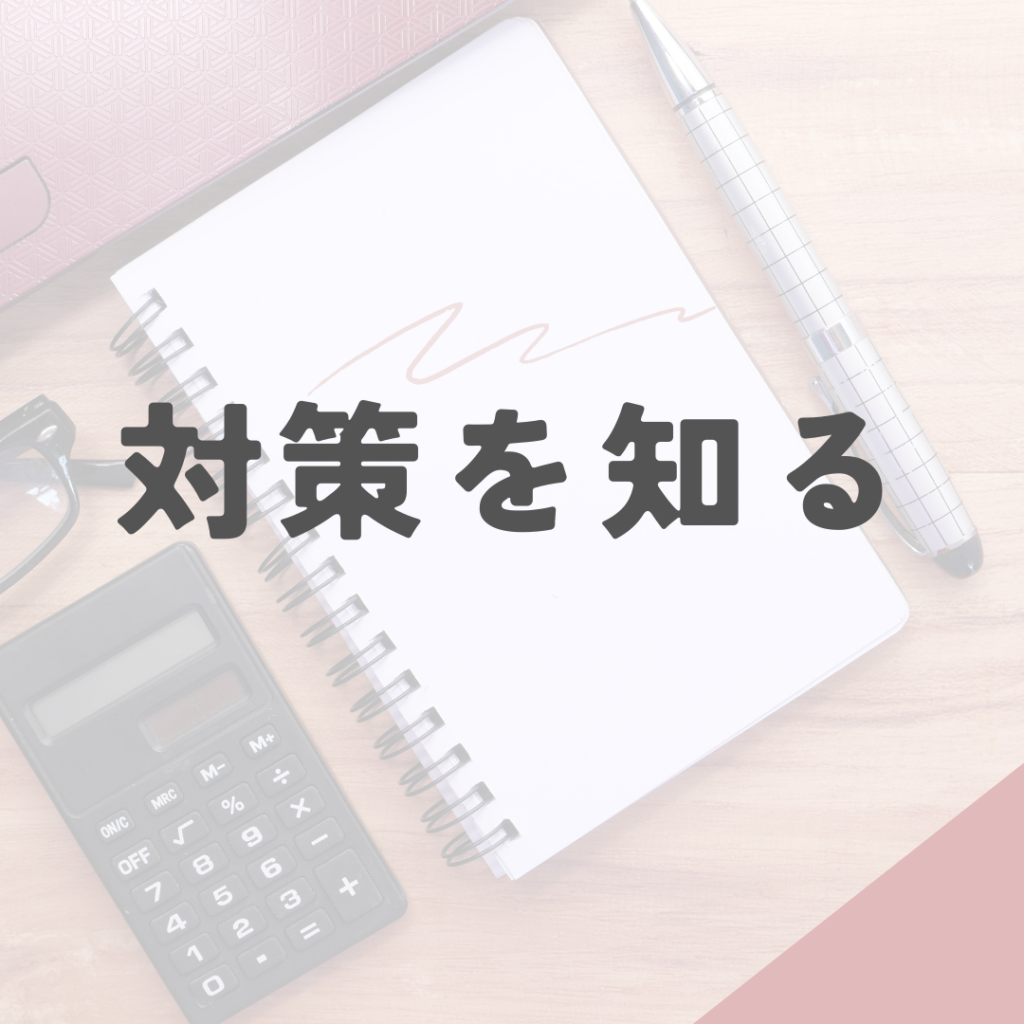
親御さんや教員の方は様々なトラブルと闘い続ける必要がありますが、対策と傾向を知っておくことで、トラブルを回避することも非常に重要です。
いじめの対策には、
いじめの現状を正確に把握することが大切です。 証言を集めて、いつ、どこで、誰がいじめをしているかを特定しましょう。また、いじめをしている子どもたちと対話し、その背景を探ります。保護者や教師と協力して、問題を解決するさらに、他の子どもたちにも配慮し、クラス全体でいじめのない環境を作ることが必要です。これらの方法を実践することで、いじめを防ぐことができます。
いじめの解決方法には、
いじめられている子どもたちの自己肯定感を高めることが重要です。また、クラス全体でルールや約束を作り、いじめのない環境を作ることも大切です。グループ作るワークや遊び、子どもへの協力や共感の精神を学ぶこともできます。いじめを解決することができます。
もめ事の対策には、
子どもたちにルールやマナーを教えることが大切です。また、取り合いやトラブルがとりあえず起こりやすいおもちゃや場所を減らすことも有効です。起こった場合には、原因を聞き出し、設定を変えることが重要です。子どもたち自分の気持ちを表現しやすい雰囲気を作ることも大切です。これらの方法を実践することで、もめ事を解決することができます。
体調不良の対策には、
感染症予防のために手洗いやうがいを徹底することが必要です。 熱中症予防のために水分補給をすることも重要です。もし、体調不良の子どもたちがいた場合には、適切に対応する必要があります。救護室を設置する、保健室に連絡するなどしましょう。
トイレトレーニングの失敗の対策には、
トイレトレーニングをしっかりと行うことが重要です。 トイレの場所を思い出させることも必要です。 トイレトレーニングの結果を保護者に報告また、失敗した場合には、怒ったりするのではなく優しく、励ますことが必要です。 トイレトレーニングは子どもにとって大きな成長の一つであり、焦らずに取り組むことが大切です。
おむつの取り替えの対策には、
保育士の人数を増やすことで、おむつの取り替えにかかる時間を短縮することができます。士たちのスケジュール管理がしやすくなります。保護者と共同でおむつ替えのルールを決めることで、子どもたちが安心して過ごせる環境を作ることができます。これらの方法を実践することで、保育園でおむつの取り替えにかかる時間を短縮することができます。
事故の対策としては、
- 同様に、遊具の点検とメンテナンスを定期的に行い、危険な場所には幼稚園を設置したり、照明を明るくするなどの対策が考えられます。
- 危険な場所には注意を書きます。
例えば、滑りやすい場所には「滑りやすいので注意してください」という表示を、駐車場には「歩行者注意」の表示をするなどの対策が考えられるあります。 - 保育士が子どもたちの動きを十分に監視する。
例えば、遊具やプールでの遊びの監視、転倒や怪我を防ぐための手を差し伸べるなどの対策が考えられます。
もめ事の対策としては、
- こどもたちにマナーやルールを教えます。 挨拶や感謝の言葉、お互いに尊重することなどを教えましょう。
そして、相手を無視する言葉や態度をとった場合には、その理由を聞き出して適切なアドバイスをすることができます。いじめや暴力の防止、マナーやルールの遵守などについてルールを決め、保護者と協力して守ることができます。
食事のトラブルの対策、
- 栄養の大切さや食べ物の生産者について学ぶ、もしくは家庭菜園などでご飯である野菜を育てる楽しさを学びましょう。
- 食事のマナーを教えます。 箸の持ち方や、食べ物を飛ばさないようにすることができます。そして、食べやすい大きさに切ったり、食べる順番を教えたり基本的なことも伝えましょう。
おやつのトラブル対策としては、
- おやつを選ばないようにルールを決めます。 例えば、おやつの順番を決めたり、一度食べられる量を決めたりすることができます。
- おやつを子どもたちに適量考える。 例えば、おやつの種類によっては、過剰な食べ過ぎを防ぐために、適量を考えることができます。
これらの対策を実践することで、保育園の問題やトラブルを予防し、子どもたちが安全で健全な環境で成長できるようにできます。教職員との協力やコミュニケーションが重要です。
~他の記事~
- 子供が産まれたけど。やっぱりワンオペ育児

- 産後のダイエットは必要?産後多くの人が痩せるワケ

- アルファベットを覚える為の学習方法10選。幼児教育の基本

- 補助金で解決?オーストラリアと家庭内暴力の実情

- アメリカと中国の子供どっちがお小遣い多いか知ってますか?日本はお金持ち説
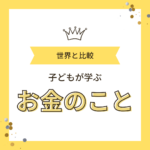
- 子供に使わせてますか?電子マネートラブルはこれからの親の悩み

- TikTokトレンドのベッド・ロッティングでストレス発散するZ世代
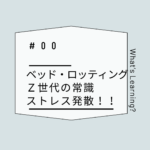
- 夫に失望する。子育ては夫婦の問題と分かっていない

- 実家で子育ては失敗する。育児が楽になるという迷信を信じた結果
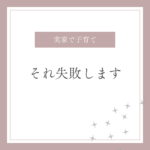
- すぐに怒っちゃう。子どもの精神力が根付く方法

- 勉強とスポーツの子育て二刀流。失敗しやすい理由はこれ

- ほらね、起業家になるなら大学に行くな?子供の進路を考える
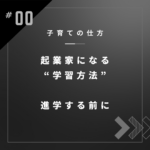
- 子どもにも妊婦にも悪影響?シーシャとスヌース知ってますか

- この夏危険な感染症は、ヘルパンギーナだけじゃない?夏休みに気を付ける
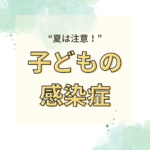
- 親注意?AIやアバターが子供に与える影響は深刻

- 子育てに影響?資本主義と子供の教育は密接にかかわる「ショック・ドクトリン」
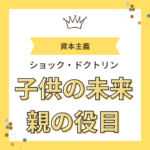
- 将来の夢は社長?MBTI式教育で起業家を育てる

- これほど便利?5Gは子育てアップデート世界が変わる

- イジメ問題とその余波を見る:危機に瀕したノースウェスタンフットボール

- 脳老化予防はKlotho(クロトー)を増やすこと。子どものころから気を付ける



